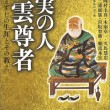「子供を愛しすぎてはいけない」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)2
<和俗童子訓の現代語訳 2>
子供がうまく育たないのは、両親、育てる人が教育について、正確なことを知らず、悪いことをやっても許してしまったり、そのまま褒めたりして、子供の本性を損なってしまっているからです。
あるいは、しばらく泣きやませようとして、嘘をついたり、だましたりして、その場しのぎの愛情を示したりする。
その愛情が本当でなければ、それはつまり、嘘を教えていることになるからです。
あるいはふざけて、怖い話をして脅せば、のちのち、臆病者になります。
幽霊や、おばけ、妖怪など事実でないお話は、聞かせないようにしなければなりません。
あるいは子供が気に入らないものについて、正しいことを言わず、子供の誤りを肯定して、とぼけていれば、おごりの気持ちが出てくるものです。
子供をもてあそんで、自分の心を満たすために、いろんな言葉を使って、困らせ、苦しめ、怒らせ、争わせると、ひがみっぽくて曲がった心を生み出し、貪ったり、ねたむ気持ちを引き出してしまいます。
それだけでなく、両親が愛しすぎると、子供が甘えてしまって両親をおそれず、兄弟姉妹をないがしろにして、家にいる人を苦しめてなんでも思うがままにして人をあなどります。
注意しなければいけないことを、むしろすすめて、怒らなければいけないことを、むしろ笑って喜び、いろんな悪いことを見聞きして、悪いことをしゃべったり、行ったりすることに慣れる。
その後、やっと大きくなり、知恵が出てきたときに、初めて注意しても、悪いことの習慣は年齢と共にますます城上達してしまい、長い時間をかけて身に付いてしまったので、本性と同様になってしまい、注意は意味をなしません。
幼い時に教えず、大きくなって突然教えて注意しても、聞く耳をもちません。
本性が悪く生まれてきてしまったと思ってしまうのは、愚かなことであり、迷いが深いことです。
生まれたときから愛情は持ちすぎてはいけません。
愛情が過ぎれば、かえって子供をダメにしてしまいます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<感想・考察>
電車の中で騒ぎちらかしている子供がいても、注意をしない親が注目されることがあります。
小さいときから子供に注意をしないと、中学生、高校生、そして大人になっても電車の中で騒いだりすることになるんだろうと思います。
うちの子も電車でよくわめきますが、静かにさせることはもちろん、誰かを蹴ったりすれば必ず怒るようにしています。
今はまだ2歳なので、意味もわからず怒られていると思いますが、意味がわかるようになったら、電車の中という空間が公共のものであることを伝えて、注意しようと思いました。
また、ご飯を食べている最中に足を机の上にのせようとする癖がありました。
行儀が悪いと言って、足を下に下ろしていましたが、それをおもしろがって何度もやる。
いけないことだと教えないといけないと思い、最後には本気になって足を叩いて怒りました。
こういったことは出来ているなーと思いますが、たまーに、私が嘘をついて言い聞かせることがあります。
それはまずいなということが今回、身にしみました。
鬼から電話というアプリもありますが、これは子供を臆病にしてしまうのかもしれませんね。
愛しすぎてはいけない、というのは言うは易し、行うは難しです。
今は、息子を一人の人間として立派に生きていけるように教えていきたいですね。
関連記事
-

-
兄弟喧嘩は神がネジ巻きをした変態的スポーツ
親でありながら、我が子のどちらかを偏愛するなどとは、ちょっと考えられないことのようです。 しか
-

-
一事を通してその最大活用法を会得させよ
流行のいかんにかかわらず「物を大切にしてエネルギーを生かす」ということは、万古不易の宇宙的真理です。
-

-
父親はわが子を一生のうちに三度だけ叱れ
父親の本務とはいったいなんでしょうか。 第一に、家族を養い育てる経済力です。 これは前にも書
-

-
わが子を勉強好きにする秘訣
家庭学習の一番の土台は、小学1年生と2年生では、国語の本を毎日必ず朗々と声に出して読むことです。
-

-
我が子をどういう人間に育てたいのか
私も全国を旅して、父兄の方々と話をしたものの一人ですが、その際、よくお母さん方にお尋ねしたものです。
-

-
「寒さと飢えが子供を丈夫にする」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)3
<和俗童子訓の現代語版 3> 厚着や、飽食は、病気の元です。 薄着で、小食であれば、病気
-

-
「子供を育てるときの心がけは人としての真心」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)7
小さいときから、 心持ちは柔らかに 人を慈しんで 情の気持ち持って 人を
-

-
子供や若者は車内では必ず立つように躾よ
一大実践目標 今から三年ほど以前に、私どもの同志の中で、とりわけ異彩を放つ山本紹之介君は、毎月
-

-
女子の教育は「家事」を手伝わせるのが秘訣
前に、「わが子に、人間としての性根を養うには、結局腰骨を立てさせるほかない」と力説しました。