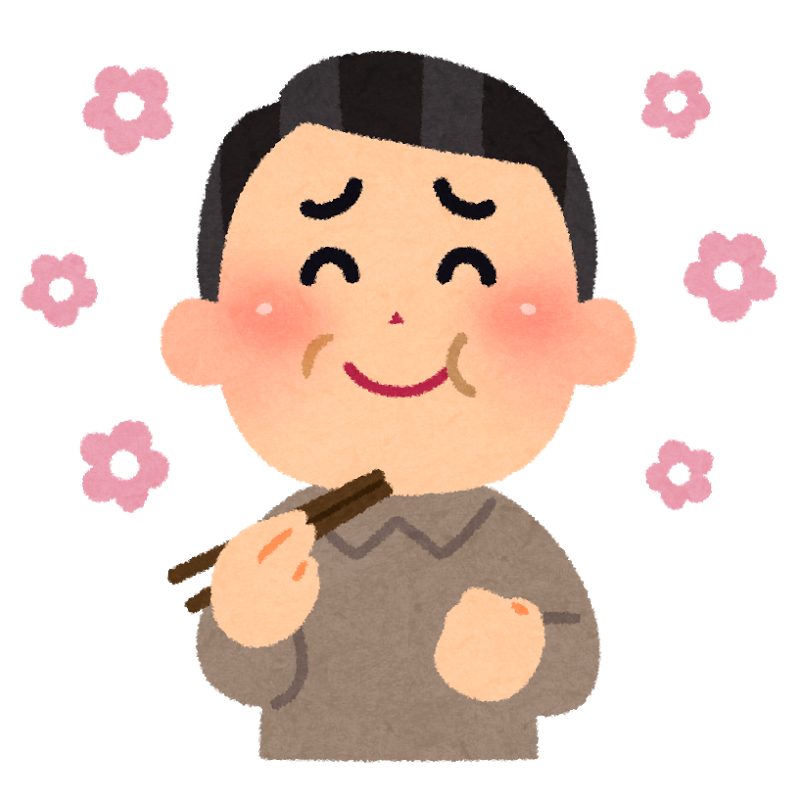十 夫婦のあり方
夫婦のきまり
私も今までずいぶんと結婚式の披露宴のお招きを受け、祝辞を述べる機会を与えられてきました。
その都度大体決まって申し上げてきたことは次の通りです。
「まず新婦のお方にお願いしたいことは、
第一、朝起きたらご主人に対して必ず朝の挨拶をなさること。
第二、ご主人から呼ばれたらハッキリと、そしてさわやかに「ハイ」と返事をなさること。
第三、主人の収入の多少に対しては、一切不平を言わぬこと。
以上の三ヶ条です。
次に、新郎たるご主人にお願いしたいことは、
第一、奥さんに対しては小言は言わないこと。
第二、奥さんの容貌に関しては一切触れないこと。
第三、妻の実家の親・兄弟はもちろん、親戚についてもけなさぬこと。
これがお互いに守っていただきたい三つのきまりです。」と。
という風に、人生の門出に当たり、若いご夫婦に説いてきたのであります。
このことは先に刊行の「家庭教育二十一ヶ条」に詳説してありますので、この書と共にぜひご一読いただきたいと思いますが、この三ヶ条はお互いに必ず守っていただきたいものです。
さて、妻たり、母たる奥さんには、この「家庭教育二十一ヶ条」をご覧いただくとして、次に家長たり、夫たる父親の方にいちばん申したいことは「小言は言わぬ」ということです。
「小言を言わぬ」とは、妻に対する大前提でなければならぬと思います。
というのは、肉体的交渉を持つ妻を教育しようなどとは、とんでもないことだからです。
それよりもむしろ「一切小言をいわぬ」ということが、最根本的態度でなければならぬと思います。
なんとなれば「結婚するまでは両眼をみひらき、よく見極め、結婚したら片目を閉じよ」と一般に言われておるように、妻への「いたわり」が根本になければならぬといえましょう。
生まれも育ちもすべて違うものが、こうして夫婦として結ばれ、家庭を持ち、子を生み、そして育て、日々の生活を共にするわけですから、思えば宿世の因縁というよりほかないでしょう。
つまり、人生の伴侶への「いたわり」が根本基盤として忘れられてはならぬわけであります。
それにつけても、近年アメリカの風潮をうけ、我が国においても離婚率が世界第三位という、まことに好ましからぬ現象ですが、この離婚原因の第一を占める性格の不一致なども、一方から言えば、自己中心的な気概・わがままが最大原因ともいえましょうが、一方からは血液型や生年月日などによる気質の洞察を誤った点もないとはいえないでしょう。
こうした面からの相性判断も、むげに一笑に付すべきではないと、私は考えています。
しかしこの点については後ほどまた述べることにしましょう。
いたわりと忍耐と賛助
ところで、わたくしは若いご夫婦にははなむけのコトバとしていつも申すのですが、人間関係のうち、夫婦関係ほどお互いに絶大な忍耐を要する関係はほかにないということです。
それゆえ、相手の欠点短所を攻めるのではなく、むしろ人間的に優れたほうが、相手の至らぬ点は背負っていく覚悟がなくてはならぬということです。
ですから、私は夫婦和合の心構えとして、1.いたわり、2.忍耐が最大の必要条件と思われてなりません。
そしてもう一つ加えるとすれば、3.賛助ということではないでしょうか。
賛助とは、平たく言えば「助け合い」ということです。
この賛助ということも、直接的と間接的とがあるわけで、たとえていえば台所仕事に直接手を下して手伝うよりも、奥さんの丹精こめた料理を褒めるということが、最も効果のある間接的な賛助ではないでしょうか。
これなら世のご主人方もその心がけ次第でたやすくできそうに思われますが、いざ実際にということになりますと、実はこれ一つが決して容易ではなく”「ウン、これはウマい」と言ってくれたことはただの一度もなく、ただ黙ってムシャムシャ食べてくれるだけです”とこぼされる奥さんの多いのも無理ないことでしょう。
ですから、世の男性諸氏に申し上げたいことは、「ウンこれはウマい!!よくできたね!」と、三日に一度くらいはぜひひとつ言い添えていただけたらと提言する次第です。
これは要するに、奥さんの努力に対する間接的な賛助精神の発露として、きわめて大事なことであり、これによって奥さんがますます腕を磨くきっかけとなり、励みともなりましょう。
絶対の禁句・禁言
それとは反対に「これはマズイ」という一言は、奥さんにとっては致命的な痛手をこうむるわけですから、これはゼッタイ口にしてはならぬ禁句でありましょう。
まさに一言の違いが、天地の差を生ずると言えます。
「ウン、これは珍しい。だがちょっと塩気が利きすぎたようだね」と言えばいいものを、これはマズイの一言で片づけられると、奥さんにとってはたまったものではないでしょう。
それから、ゼッタイの禁句ともいうべきもう一つは、不器量、不器用、不細工、不恰好というようなコトバを奥さんに対してはゼッタイに発してはならぬと思います。
それは我々男性にとっては、”能無し”とか”甲斐性無し”というコトバに相当するわけで、たとえ夫自身は内心それを認めていたとしても、妻からそれを言われると、これほど骨身にこたえる鋭利な一言はないといえます。
それというのも、男性にとって力量・能力・稼ぎ高などは、男の第一条件でありますように、容貌・感覚・器用さは女にとっての第一条件であるからです。
ですから、その根本条件に対する軽視・無視・蔑視こそ、男・女両性にとって実に堪えがたいものとなるわけです。
したがって、これらの一連のコトバはゼッタイ口にしてはならぬ一言として、たとえ冗談にも使ってはならぬのであります。
「森信三先生 父親人間学入門 10」 寺田一清著
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
夫婦関係は子供がいないときは恋愛の延長線上でもそれなりにうまくやっていけますが、子供が生まれると大きく変わる。
妻から母になる、とでもいうのか、優先順位が変わり旦那のことは二の次となる。
まあ、これは私の家庭かもしれません。
旦那からすれば、仕事に打ち込みたい盛りなのでむしろよかったと思うこともしばしばあります。
ただ、私は共働きですので、子供の面倒をみないと後で癇癪玉となって弾けとびます。
そうならないよう、週末はしっかりと子供と遊ぶようにしています。
「小言を言わない」というのは旦那としてはもちろんですが、全般に言えることではないでしょうか。
小言を言って楽しい人はいないし、幸せになる人はいません。
母から子供への小言なども良い影響はないと思います。
何も言わず受け止めるくらいの人間の器を誰もが持っていれば、家庭はもちろん、職場や組織がうまく回っていきますね。
結局のところ、ここで森先生が言っているのは夫婦と言っていますが、人間社会全般に言えることだと思います。
要は、相手に対する思いやりをもって接しなさい、ということですね。
それを夫婦の場合には、こう、と具体的に諭してくれている。
小学生の時から言われていることですが、常に意識していたい「思いやり」。
妻にも「思いやり」を持った言動で接していこうと思います。
関連記事
-
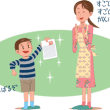
-
子どもは見てる 知ってる 感じてる
こころの察し ひとかどの教育者のような口調で述べてまいりましたが、実際のところ、学校教育の現場に立
-

-
時には飢餓感を体感させよ
「物が豊かすぎると、心はかえって衰弱する」と言われていますが、これは宇宙的真理のようです。 近
-

-
一事を通してその最大活用法を会得させよ
流行のいかんにかかわらず「物を大切にしてエネルギーを生かす」ということは、万古不易の宇宙的真理です。
-

-
子供を褒めてはいけない?
人の徳の中でも悪いのは、高慢なことです。 高慢だと自分はいつも正しいと思い込み、悪いところに気
-

-
母親は家庭の太陽である
偉大な大業の責任者 いよいよ私の後述も、最終の章を迎えることになりました。 思えば第一章より
-
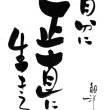
-
「子供を正直に育てたいなら、親こそ正直に」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒) 5
<和俗童子訓の現代語版 5> 幼い時から、心や言葉は正直に、嘘はないようにしましょう。 もし人を
-

-
朱に交われば赤くなる 子供は白いキャンパスのような物
子供の教育には、交流する友達を選ぶことを大事にしましょう。 子供が生まれついて善で、父の教えが