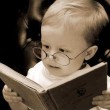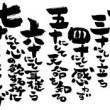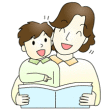子供を褒めてはいけない?
人の徳の中でも悪いのは、高慢なことです。
高慢だと自分はいつも正しいと思い込み、悪いところに気づきません。
間違いを聞いても受け入れません。
そのため、悪を改めて、良い徳に進ませることは困難です。
たとえ、すぐれた才能があっても、高慢で自分の才能に自惚れて、人を侮れば、これは凶悪な人間というしかありません。
だから子供の良い行い、才能にあふれたことを褒めてはいけません。
褒めれば高慢になり、気持ちをコントロールできず、自分が至らないところ、不徳なところに気付かなくなります。
自分は頭がいいと思うと、他から学ぼうと思わず、学問を好まず、人の教えも求めなくなります。
もし父が愛におぼれて、子供の悪いところに気付かず、素行が悪くてもべた褒めし、大した才能がなくても優秀だ、と思うのは愚かなことです。
良いことを褒めれば、結果的にその良いことを失い、上手なことを褒めれば、結果的にその上手なことを失います。
子供は絶対に褒めてはいけません。
その子にとって害になるだけでなく、人にも愚かなことだと思われて、悔しいことではないですか。
親が褒めた子供は、たいてい良くならず、学問も技能も拙いものになります。
篤信は昔、こう言いました。
「人には3つの愚がある。自分を褒め、子供を褒め、妻を褒める。これらは全て愛に溺れるがゆえである」
(和俗童子訓より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【感想・考察】
子供を高慢にさせてはいけないですが、褒めないほうがいいというのはどうなんでしょうか。
常に厳しく育てよ、ということだと思いますが、萎縮してしまうと思います。
時代が違う、という使い古された言い訳かもしれませんが、昔はそれでもよかったのかもしれません。
いや、おそらく、これは江戸時代の上流階級の子供向けに書かれたことなので、極端な教えになっているのかもしれませんね。
上流階級の子息、とくに世継ぎともなれば、取り巻きはもちろん、多く、その中でも取り入る人間がいるかもしれません。
甘い言葉をかけられやすい子供たちだからこそ、父としては厳しく接するべき。
そんな思いが込められているかもしれません。
私自身は子供に対して褒めが8割、躾のために叱るのが2割くらいになっています。
理想は褒めが9割、叱るのが1割くらいが理想だと思っています。
普段は褒めて、叱るときは烈火の如く叱る。
子供を伸ばすことを主に考えて、たまーにおかしいところを剪定する。
それが理想ですね。
関連記事
-

-
母親は家庭の太陽である
偉大な大業の責任者 いよいよ私の後述も、最終の章を迎えることになりました。 思えば第一章より
-

-
朱に交われば赤くなる 子供は白いキャンパスのような物
子供の教育には、交流する友達を選ぶことを大事にしましょう。 子供が生まれついて善で、父の教えが
-
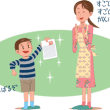
-
子どもは見てる 知ってる 感じてる
こころの察し ひとかどの教育者のような口調で述べてまいりましたが、実際のところ、学校教育の現場に立
-

-
「早期教育でなければ意味が無い」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)8
子供を教育するには、早いほうがいいです。 それなのに、あまり教育を知らない人は、子供を早くから
-

-
「教育は早いうちから」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓に学ぶ 1
「和俗童子訓」は江戸時代の学者、貝原益軒が1710年に著述した書物で、日本で最初にまとまった教育論書
- PREV
- 子供には謙譲の気持ちを教えよう
- NEXT
- 子供の先生を選ぶ基準は才能?それとも人柄?