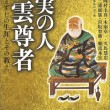わが子を勉強好きにする秘訣
家庭学習の一番の土台は、小学1年生と2年生では、国語の本を毎日必ず朗々と声に出して読むことです。
そして堂々と自信を持って読めるようにすることです。
これがあまりにカンタンなことなので、朝のあいさつと返事もそうですが、この事がいかに大事かということのわかる人は少ないですが、実に大事なことです。
これは農業でいったら「土」を肥やすのに当たります。
また、コンクリート建築でいったら、地下工事にあたるもので、最も大切な土台づくりです。
毎日、必ず親子がかわりばんこ読むのです。
それには、子どもが学校から帰ってきたら「暑かったでしょう」とか「寒かったでしょうね」などと言いながら、すぐに続けて「今日のおやつは、あんたの好きな○○なのよ」と言う。
これが大事なことです。
というのは、子どもから催促されてからでは、せっかくのおやつも値打ちが2〜3割引になるということを母親たるもの知っておかなければいけません。
万事が後手に回っては、ダメだということです。
次には、おやつをやる「場所」が大事なんです。
それには、親と子どもが机に向かい合ってやるんです。
でないと、たべてしまうと、もうつかまらん子がいますから。
おやつのやり場所一つ知らない親御さんさえあるんですからね。
さて、わが子がおやつを食べている間に、一応その日学校であったことを聞くわけです。
そして食べ終わったら「さぁ、それではお勉強をしましょうね」と言うわけです。
すると、おやつを食べた義理があるので、いまさらにげるわけにもいかんでしょう。
このように、勉強への手はずを、水も漏らさんように進めて行くわけです。
そしていよいよ、読本の朗読ですが、それには親がいっぺん、子がいっぺん、代わりばんこに各々20回以上読むのです。
もし内気な内向性の子どもさんだったら、親が二へん、子どもがいっぺん、そして子どもが20回に達するまで読む。
ですから親は40回読むわけです。
このように親がまず軌道をつくって、その上にきちんと車を乗せて発車させるというわけです。
しかし、多くの親御さんは、こういうことは何もしないで、ただ「勉強しなさい!勉強しなさい!」と言うばかりですが、それではやらないのが当たり前です。
やる子のほうがよほど感心なお子さんというわけです。
ついでに、内気なお子さんを直す秘訣は、読本を朗々と自信を持って読ますというただ一つだけです。
内気なお子さんでも、普通の発表と違って読むのですから、土台があって、それを声に出して、しかも同じところを何度でも読むのですから、だんだんと慣れてくるわけです。
こうしていると、内気な子どもさんでも次第に積極的になってくるわけです。
物事というものは、最初にまず一つの事柄を徹底的にぶち抜かねばダメだということです。
同様に我々人間も、一つのことを徹底することによって、人間としての性根がピーンと立ってくるわけです。
ですから、毎日必ず国語の本を親子で朗読する、というこの家庭学習を軌道に乗せる根本作業をうっかりしていて、一年生や二年生ではやらさずにいたお母さんも、三年生、四年生でもよいですから、ぜひどこかで、せめて丸一年間おやりになるのがよいでしょう。
そうすると驚くほどメキメキと力がついてきますから。
それから第二の勉強は、これはなかなか難しいことですが、2年生、3年生、4年生という3カ年の算数は「一つもわからないものをなくす」ということです。
これはお母さん方がよほどの強い決意をしないとやれません。
しかし、これさえやり通せば、五年生から以後は、母親としての直接責任はなくなります。
それというのが、これさえしておけば、五年生になったらもう実力がついていますから、自分で勉強をするようになるからです。
同時に五年生になったら親が教えないほうがいいくらいです。
というのは、もう自分で勉強するようにしなくてはダメな年頃だからです。
その代わりに四年生までは徹底的に教えるわけです。
そして、2〜4という3年間の算数は、一つもわからない問題をなくしてしまうのです。
以上がもし完全にできたら、それで家庭学習における母親の責任は完全解除と言えるわけです。
そしてわが子が5、6年生になったら、もし尋ねられて、しかも母親に教える力があったら教える。
しかし子どもから尋ねられないのに詰め込むと、中学の二年生になったら急にダメになって、どうにも手がつかなくなります。
それは自発的な学習態度が身についていないからです。
ですから中学、高校になったら、家庭学習に関する親の責任はいわば間接責任で、間接責任とはただほめることだけというわけです。
そしてそれには、わが子が机に向かっているのを見たら「また、今日もお勉強かね、近頃なかなかやり出したわねえ〜」と、こういう調子なら誰だってやれるはずです。
そして「これじゃ紅茶の一杯も出さなくちゃならないわね」と言って、皆さん方はお勝手へ行って紅茶の支度をするんです。
この場合、ほめるのは後ろからほめるのが秘訣です。
というおんは前へ回って見たら、弟の漫画を召し上げて読んでいるかもしれないからです。
それを見たらほめようにもほめられませんから、「知らぬが仏」で後ろからほめるんです。
ところが紅茶が出来上がったら、今度は前から出すのです。
すると紅茶のできる10分ほどの間に、漫画の本が英語の教科書に化けているんです。
そこでそれを見てまたほめてやるんです。
「近頃はこんな難しいものが分かるようになってくれたのね。やはり、やり出したせいだわね」と。
こうして後ろからほめられ、前からほめられますから、子どもとしても勉強せずにはいられないようになるのです。
そしてこれが先に申した間接指導というものなんです。
ですからわが子が中学や高校へ行きだしたら、親としてはもはや「勉強せんか」などは一切言わないように、それこそ首がちぎれてもこれだけは言わぬことです。
そしてほめること一本槍で貫くわけわけです。
母親自身、自分では教える事のできない身なのに、それを忘れてわが子の顔を見れば「勉強しなさい」「勉強しなさい」などと言う資格は毛頭ないということを、徹底的に知ることが一切の根本です。
そして親としてやれることはただ「ほめる以外にない」ということを、骨身に刻んで心得るというほかないわけです。
「家庭教育の心得21 母親のための人間学」(森信三著)12より
——————————-
小学4年生までは親が率先して勉強へと導いて、5年生以降は子ども自主性に任せる。
間接責任として、とにかく勉強していることを褒めるようにする。
できている家庭はなかなかないんではないでしょうか。
そして、勉強をさせるところまでを用意周到に考えている家庭もなかなかないと思います。
勉強させる子にするには、親のほうがよく考えて道筋を作っていく必要があるんですね。
うちの子は、2014年12月時点はまだ2歳なので勉強させるということはありませんが、何かができたら、とにかく褒めるようにしています。
階段を一人で上りきったり、下りきったりしたら、頭をなでてやる。
ご飯を全部食べたら「すごいねー、全部食べたんだ!」と褒める。
そんな風にして褒めるようにしています。
そうすると、嬉しそうな顔をするので、良い習慣化につながって行くんだろうと勝手ながら期待しています。
勉強させられないのは、子どものせいではなく、親の責任ということを肝に銘じておきたいと思いました。
関連記事
-

-
子供の前では絶対に「夫婦喧嘩」はするな!!
昨今の青少年の非行化は今なお大きな社会問題の一つです。 その根本原因をつきつめると、一言でいえ
-

-
一事を通してその最大活用法を会得させよ
流行のいかんにかかわらず「物を大切にしてエネルギーを生かす」ということは、万古不易の宇宙的真理です。
-

-
わが子を丈夫な子にする秘訣
体が弱くて、しょっちゅう病気をしがちなお子さんを持っておられるお母さんは、どんなことより、この点を一
-

-
子供には小さいときから礼儀を教えよう
礼儀は世の中に常にあり、人として生きる作法です。 礼儀がないのは人間の作法ではありません。動物
-

-
母親は家庭の太陽である
偉大な大業の責任者 いよいよ私の後述も、最終の章を迎えることになりました。 思えば第一章より
-
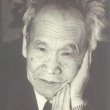
-
子供の先生を選ぶ基準は才能?それとも人柄?
子供に学問を教える時は、初めから人柄の良い先生を探しましょう。 才能や知識があっても、善徳を持
- PREV
- 兄弟喧嘩は神がネジ巻きをした変態的スポーツ
- NEXT
- 時には飢餓感を体感させよ